2.市街地の形成と近代的商業の胎動
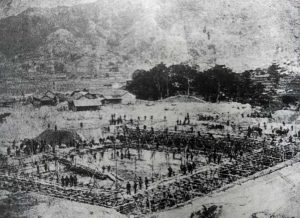
明治20年ころ
出典:『呉市史』第3巻
多年にわたり、平穏な生活を続けてきた呉浦の住民の生活は、鎮守府が設立されることが決定し大きく変化した。呉鎮守府開庁の影響を、のちに旧呉市を形成する地域の戸数・人口によってみると、目をみはるばかりである。明治19(1886)年まで1万5000人前後で推移してきた人口は、翌20年の1万8450人までになり、24年には2万3312人と、この時期まで急上昇している。19年11月に開始された呉鎮守府の建設工事が、20年以降に本格化し、24年に一段落したことを反映しているわけである。
4か村合計では、それほどの変化はみられなかったものの、明治19年には宮原村の人口が激減し、和庄村と吉浦村(川原石・両城地区)のそれが増加している。全国から呉浦に人口が流入したことに加え、宮原村の呉町にあたる部分を中心とする約77町歩が海軍用地に買収され、1,023戸の住民が同年8月15日を期して立ち退きを命じられたことによる。呉町の住民が、のちの呉駅前から市役所付近へ412戸、宮原村内高地部へ385戸、海軍用地付近へ44戸、川原石・両城地区へ182戸というように移転しなければならなくされたことにもよる。
立ち退きを命じられた住民は、海軍用地の買収が進むにつれて土地化価格が急騰し、支払いを受けた土地代と移転料で新たな土地を購入し家屋を新築することが困難になるという問題に直面した。とくに保証金の支払いを受けることのできない借家人には、家屋の不足からくる家賃の高騰がもっとも深刻な問題であった。当時の状況をよく知る呉浦の医師 佐々木進は、『呉港衛生記談』において、「赤貧ノ為借家ナキ者ハ一時、……海辺ニ帆柱ヲ建テ、帆等ヲハリ、往古時代ノ家ノ如ク、只、雨露ヲ凌」いだと書き残している。
一方、呉鎮守府の工事とともに市街地の形成もすすめられた。鎮守府の工事で、和庄村から宮原村をへて警固屋村にいたる道路のうち宮原村の部分が中断されたことにより、これにかわる道路として警固屋村字瀬の向から鍋峠を越えて宮原村の山腹を迂回し、和庄村明法寺下にいたる新道が計画され、明治20年に開通した。これと前後して市街地形成の根幹をなす、海軍第1門から和庄村十文字新開にいたる延長324間(約583メートル)、幅10間(約18メートル)のほぼ南北に走る国道と、和庄村檜垣の海軍監獄下から堺川、二河川をわたり川原石にいたる幅8間(約14メートル)のほぼ東西を貫く県道が完成した。このうち国道は和庄大通りとか本通と呼ばれ、呉公論社発行の『呉』によると、「一種の模範的道路とも称す可く、夙とに並樹の栽植せらるゝあり、陽春三月の候には、柳桜をこきまぜて織り成すてふ、都大路の春の錦に異ならず」と描かれている。このほかにも川原石から吉浦村へ、荘山田村の浜田から焼山村へ、和庄村から阿賀村にいたる道路がほぼ前後して完成している。道路の建設は、家屋の建築を促進させることになり、「呉港家屋建築制限法」にしたがい、本通をはじめとする沿道に家並みが出現、急速に市街地が形成されることになる。
呉鎮守府の設立と市街地の築調により、呉浦の商業は一変した。軍港の開設にともなう人口の急増は、日用品をはじめとする消費財の需要を喚起した。この需要をになったのは、その多くが一攫千金の夢をもって県内外から集まってきた他地方や呉町の商人であり、農地を手ばなして農民から商人に転換した人たちもあった。
当初多くの商人は、和庄村の舟入に接する湯裂きに近い通称南京町(のちの元町)に露店のような仮店舗をかまえた。しかし街路が整備されるにともない、商店街としてのにぎわいは、しだいに本通筋へと移る。また呉港に民間船の出入が禁止され、川原石が新たな商港になり、外来者とともに呉町から商人が集団移住したことにより、この地が商業地として注目されるようになる。
